慈姑(くわい)ってどんな野菜?
- ショウゴ オオタ
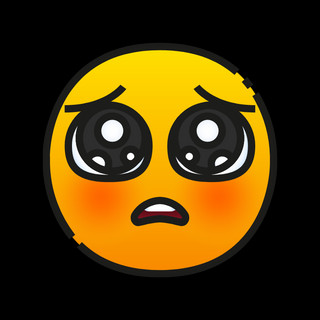
- 2024年3月1日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年6月25日
おせち料理などで使われる、慈姑(くわい)という野菜をご存じでしょうか?

日本では、古くからおせち料理などで親しまれている慈姑(くわい)ですが、「なぜ、おせちに慈姑(くわい)が入っているのか?」
どのようにして、食用になったのか? ご説明いたします。
目次:
1.慈姑(くわい)とは?

慈姑(くわい)とは、水生多年草のオモダカ科オモダカ属の植物です。
オモダカは日本各地に生息する植物で、水田や用水路で多く見られます。
葉が、矢印のように尖っているのが特徴的です。
上の画像と下の画像を見比べると、葉の形が非常に似ていることが分かると思います。
上の画像は慈姑(くわい)の葉、下の画像は自生したオモダカになります。

慈姑(くわい)は、オモダカ科の栽培品種になります。
1-1.慈姑がお節料理に使われているのはなぜ?

お節料理とは、季節の節目に食べる料理のことを言います。
元旦には、年神様をお迎えし、一年の豊富と家族の安全を祈願する料理として、お節が食べられるようになりました。
お節料理に使われる食材にはそれぞれ理由があります。
黒豆「まめに働けるよう」
こんぶ「よろこぶ」
数の子「子だくさん」
など、食材それぞれに願いが込められています。
では、慈姑(くわい)はどうでしょうか。
慈姑(くわい)
目が出て「めでたい」「自立や出世」と、縁起の良い食材として使われています。
八角形にすることで、「万年長寿」長生きするといった意味も込められ、角ばった形にして使われることが多いのです。
このように、慈姑(くわい)はとても縁起の良い食べ物としてお節料理の中で使われるようになりました。
2.慈姑(くわい)の由来

なぜ、慈姑(くわい)と呼ばれるようになったのか?

慈姑(くわい)の葉が、土を掘り起こす鍬(くわ)に似ており、鍬(くわ)の葉の下にできる芋のことを「くわいも」と呼ぶようになり、
いつしか「くわいも」から「くわい」と呼び方が変わったそうです。

確かに、三角鍬と慈姑の形は、よく似ていますね。
2-1.慈姑(くわい)の種類
実は、慈姑(くわい)の種類は、3種類あります。
「びんご慈姑の里」が作る慈姑は、青慈姑(あおくわい)といわれる品種で流通量が一番多く、馴染のある慈姑(くわい)だと思います。
田んぼの「ティファニーブルー」と言われるキレイな色が特徴です。

青慈姑(あおくわい)の他に
白慈姑(はくくわい)
吹田慈姑(すいたくわい) の2種類が存在します。
青慈姑(あおくわい)、白慈姑(はくくわい)、吹田慈姑(すいたくわい)はどれも味や食感が違いますので、気になる方は食べ比べてみてください!
3.まとめ
以上で、慈姑(くわい)についての説明をおわります。
慈姑(くわい)は生産量が少なく、慈姑(くわい)の栽培や収穫のために作られた専用の機械はありません。
ですので、植え付けから収穫まで全て手作業で行われます。
だからこそ、私たちが愛情をこめて作った、びんご慈姑の里の慈姑(くわい)を、多くの人へ届けたいと思っています。
びんご慈姑の里では、慈姑(くわい)のネット販売をしています。
ご興味のある方は、ぜひ販売ページもご覧ください。
.png)



Comments